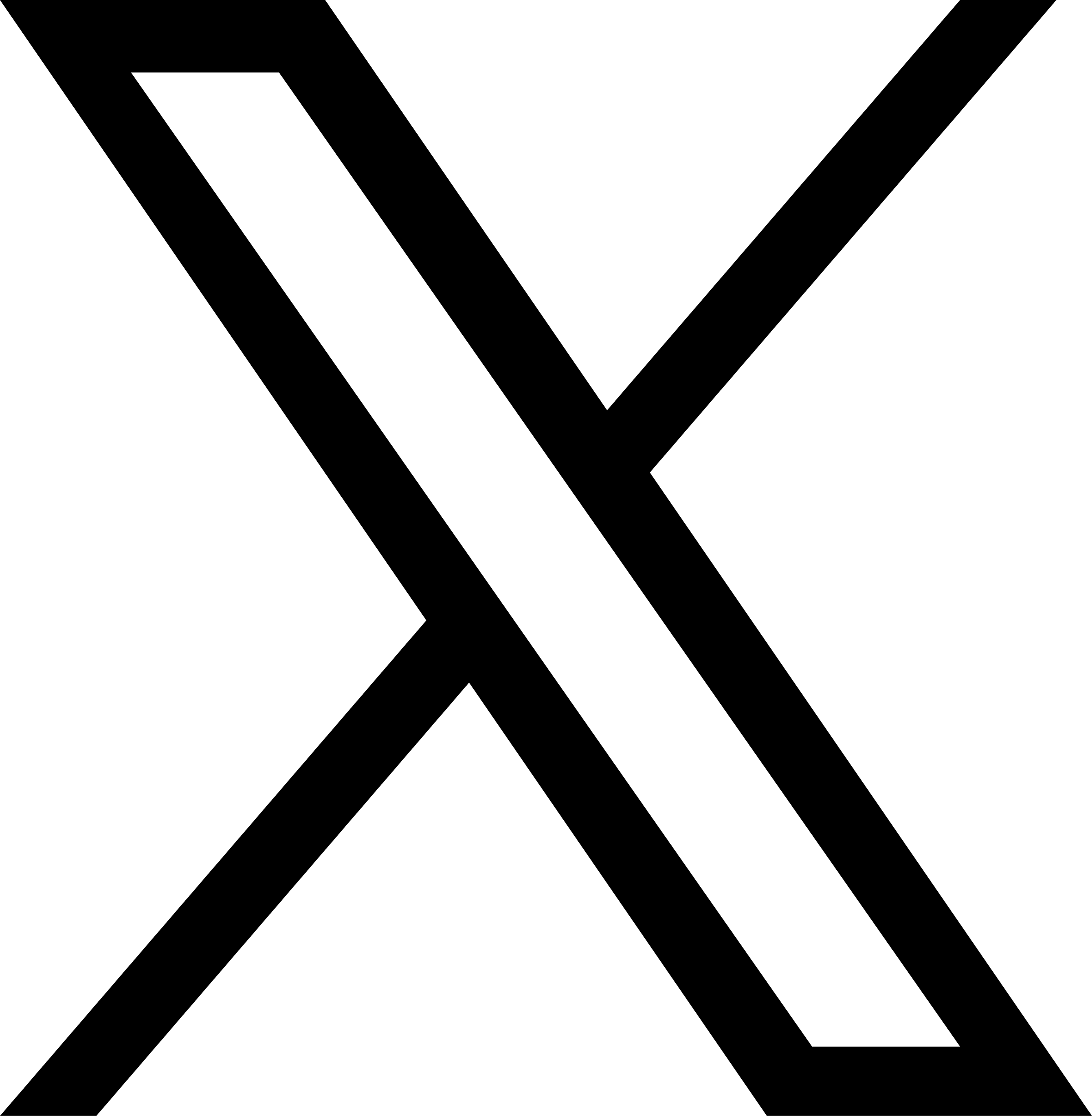電流のおはなし
電気とは?
「電気」とは、「電荷」の移動や相互作用で生じるエネルギーです。
では「電荷」とは何でしょうか?電気そのものは目に見えません。しかし日常生活において、(+)と(-)という表現を目にすることがあります。例えば、電池にも(+)と(-)が使われていますよね。これが「電荷」を指しています。電荷とは物質が持つ電気のことをいい、(+)を正電荷、(―)を負電荷といいます。
それでは、この電荷の存在を確認するために、簡単に実験してみたいと思います。まず、乾いた絹の布とガラス棒、それから小さな紙片を用意します。そして、第1図のように絹の布でガラス棒をこすって紙片に近づけると、紙片はガラス棒に吸いつきました。これは物質が持つ「電子」という負電荷が、摩擦によってガラス棒から絹の布へ移動したことによるもので、それまで均等に保たれていた正電荷と負電荷のバランスに偏りが生じたことによるものです。この現象を「帯電」といいます。
電気を帯びた物質には電荷の相互作用が発生し、磁石のS極とN極のように、電荷も正電荷と負電荷は引き寄せ合い、正電荷同士と負電荷同士を近づけると反発しあいます。引き寄せあう力を「引力」、反発しあう力を「斥力」といいます。そして、この引力や斥力の電気的な力を静電気力と呼びます。
ガラスは電子を出しやすい物体なので、電子(―)を絹の布へ移動させました。そうするとガラスには陽子(+)が多く残るので、正に帯電した状態となります。このガラス棒を小さな紙片へ近づけると、引力によって紙片が持つ電子(―)を引き寄せようとすることでガラス棒に紙片が吸いついたのです。
さて、物をこすると電気が生じることがわかりましたが、一体この電気はどこから生まれたのでしょうか。もう少し詳しく調べてみましょう。
“電気”と“電子”
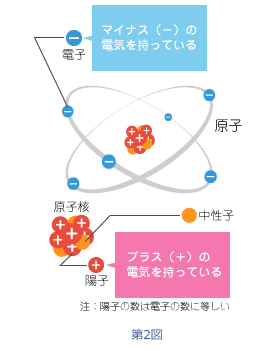
すべての物質は原子と呼ばれるごく小さな粒子からできており、原子は原子核と電子から構成されています。(+)の電荷をもった陽子と(-)の電荷をもった電子が同数であれば、電気的に中性状態であるといえます。このとき、電子は原子を構成する軌道(殻)の外に出ることはありません。
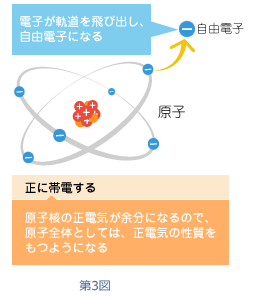
ところが、電子には外部から刺激やエネルギーを受けると第3図のように軌道から飛び出したり、逆に飛び込んでくるような電子があります。このような電子を「自由電子」といいます。つまり一般的に物質の中性状態から電子が不足すれば正に帯電し、電子が過剰になれば負に帯電します。
また、自由電子は原子との結びつきが弱い電子であり、特に金属のような電気をよく通す導体に多く存在します。電流が流れるのは、自由電子が移動することによって成り立っており、物体が電気を通すか通さないかは、自由電子の有無によります。
電流のしくみ
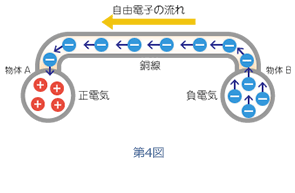
第4図のように、正の電気をもった物体Aと負の電気をもった物体Bを1本の銅線でつないでみます。するとBの(-)は銅線を通ってAに流れ込みます。これはAの(-)の不足によって、Bから自由電子がAの不足電子を補おうといっせいに流れ出したことによるものです。この自由電子の流れが電流をつくります。
しかし、電流の流れる方向と電子の流れる方向は逆方向となります。その昔、「電流は(+)から(-)に流れる」と定義されましたが、これが広まったのちに自由電子が発見され「自由電子の流れが電流をつくる」という事実が判明しました。よって、理科の授業などでは「電流と電子の流れは逆方向である」と教えられています。
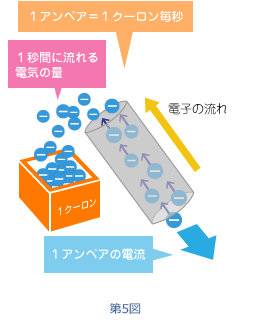
第5図のように、ある電線を1秒間に1クーロンの電荷が流れると、これを1A(アンペア)の電流が流れたといいます。
電流とは電荷(電子)の流れですから、1秒間に流れる電荷で電流の大きさを表わすことができます。電荷(電気の量)の単位をクーロンといい、1秒間に流れる電荷を電流の単位としてアンペア(A)といいます。